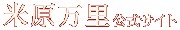このページでは、米原万里ゆかりの方が思い出を披露してくださいます。
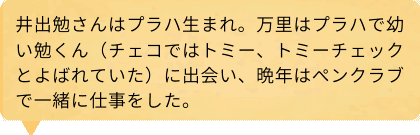 2017.6.1
2017.6.1  ◆井出勉 「マリ・ユリがいっぱい」 3才から4才のアルバムにはマリ・ユリと撮った写真が並ぶ。マリとユリのそれぞれの手をひいて、真ん中で楽しそうにしている。  古い写真アルバムの一枚には、母の手でこう書いてある。「万里が入院。お見舞いに。ユリと」。セピア色というわけではないが、古い白黒の写真では、病院の外の通りでユリと二人で並んでいる。  場所はプラハ。東欧の古都が、場違いな東洋人の子どもたちをおしゃれに引き立てる。 記憶はよみがえらない。ご両親に連れられ、マリ・ユリ姉妹がプラハに到着したのは、私が3歳の時、その出会いから1年ほどで私は両親と日本に旅立った。 とても幼い頃のことも、なにかしらは覚えているものだが、私のプラハの記憶は、子どもなりに完璧に話していたチェコ語が、帰国後半年で日本語に置き換わるうちに、すっかり消え失せたようである。 マリ・ユリは多感な少女期をプラハで過ごし、その鮮明な記憶はご存じの通り、米原万里さんの著作によみがえっている。 その後、マリ・ユリが日本に戻り、勿論、私たちは再会した。マリ・ユリには私の記憶があり、私にすぐ駆け寄ってくる。私は何か心の奥にある懐かしい記憶をたぐる。兄弟のいない私にとって、姉二人がいたらこうなのかというような思いが、その時こころにふと浮かんだのを覚えている。 プラハで生まれた私は、マリ・ユリがチェコにあらわれるまで、日本人はおろか、東洋人の子どもを見たことがなかった。そしてその後1年間ほど、マリ・ユリとプラハで一緒に過ごしたが、日本人の子どもといえばマリとユリしかいない。いま思うと、幼い私にとりマリ・ユリは絶対的な存在感だった。 言葉とともに失った記憶だが、舌の記憶は残り、本場のチェコ料理のことを三人でなつかしく語り合ったこともあった。マリ・ユリは日本で料理の再現にいどみ、東欧・ロシア料理をごちそうしてもらうと、文字通り、“同じ釜の飯を喰った”ことが確認できた。 プラハを去り、帰国の途について、私は両親とモスクワ・イルクーツク経由で北京に到着した。翌朝、外に出た4才の私は、北京の公園で遊ぶ大勢の中国の子どもたちを見て、チェコ語で叫んだと親が後に語ってくれた。 「大変だ。マリ・ユリがいっぱいいる」 大人となり、米原万里さんがペンクラブの仕事でプラハに誘ってくれた時に一緒に行けなかったのが心残りである。  2003年10月、Bunkamura ドゥマゴ賞授賞式にて。 (受賞作品は『オリガ・モリソヴナの反語法』) Tweet |
| プロフィール 井出勉(いで・つとむ) |
| 1957年チェコ・プラハで生まれる。上智大学外国語学部イスパニア語学科卒。スペインの大学、フランスの大学院で学ぶ。MBA(経営学修士)。日本航空に30年勤務。ジャパン・プラットフォーム初代事務局長。現在、日本ペンクラブ事務局長代理。著書に「あした、世界のどこかで」共著「あてになる国の作り方」。 |
|
『思い出話々』とは 米原万里のエッセイ「単数か複数か、それが問題だ」(「ガセネッタとシモネッタ」所収)に由来する。 ロシアからやってくる日本語使いがそろいもそろって「はなしばなし」という奇妙な日本語を口走る。(略)…この日本語もどきの版元が判明した。日本語学の第一人者として名高いモスクワ大学某教授。 「日本語の名詞にはヨーロッパ諸語によくある複数形はない。しかし一部の名詞にはインドネシア語などと同様、反復することによって複数であることを示すルールが適用される。たとえば、花々、山々、はなしばなし……」 |
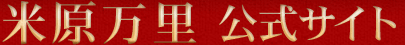
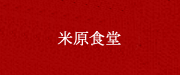
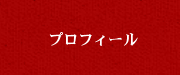
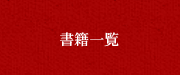
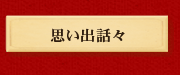


 PageUp
PageUp