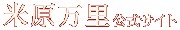このページでは、米原万里ゆかりの方が思い出を披露してくださいます。
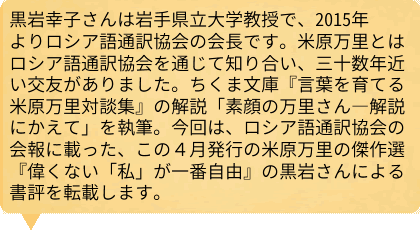 2016.6.14
2016.6.14  ◆黒岩幸子 米原万里さん没後10年の新刊書に寄せて(1) あの訃報から10年が過ぎようとしているこの春、思いかけず万里さんの新著が届き、また彼女の懐かしい声を聞くことができた。 米原万里(佐藤優編)『偉くない「私」が一番自由』文春文庫、2016年4月(720円+税)
*
ユニークな味わいは、ロシア料理でとても大切な「第一の皿」に出てくる初公開の東京外国語大学卒業論文だろう。後の文筆家としての米原万里の三つの特徴を内包する原本のようだ。
まず、人間存在への尽きない関心。テーマはネクラーソフの生涯についてだ。副題に「作品とその時代背景」とあるが、何よりも詩人の強烈な個性に惹かれているのは明らかだ。自然や概念は後景で、焦点は常に人間そのものにあるのは学生時代から変わらない姿勢なのだろう。
次に、文章力。読点無しで3行近く続く文が頻出し、これは後年のエッセイではありえないのだが、その長文がなぜかするっと読める。文の持つリズムと内容の明快さのおかげだろう。彼女の簡潔な文章は、時間勝負の通訳業を経て紡ぎだされたものと思っていたが、もっと早くに獲得されていたようだ。
最後に、ユーモア。本人はまじめに書いたつもりかもしれないが、結論部に卒論〆切期限を守れなかった「私」が出てきて、理由を説明するかと思えば、「これ以上は、愚痴になるので言わないことにする」と切り上げ、さらには、疲れたので次の研究まで1年ぐらいの休養を示唆するあたりは、読者(指導教官)を楽しませるサービスかと疑ってしまう。末尾に「提出期限のお詫びとお礼」が露和両文で記されているのも、万里さんらしい律儀な厚かましさが出ていて笑える。論文全体から語りかけ、読ませようとする意志が感じられる。
なお、ともに掲載されている指導教官の審査概評が秀逸だ。この卒論の長所、短所、詩人の伝記を書くにあたり重要なこと、軽いユーモアを含む暖かい励ましなどが凝縮されている。東京外大ではこれほど丁寧に卒論を講評するのかと感心したが、万里さんは例外なのかもしれない。同じ東京外大の卒論でも、「文章が生硬であり、誤字、脱字が目立つ」という超短文の講評をもらって打ちのめされた人もいるようだから。もっとも、これは小説の中に出てくるので実話とは限らないが。(亀山郁夫『新カラマーゾフの兄弟 上』河出書房新社、2015年、33頁)。万里さんの卒論の講評にも「誤字とともに生硬な表現が散見」の件がある。学生時代にそういう文章を書く人たちは、将来ダイナミックな文筆活動に入る可能性が高いということかもしれない。
話がそれたが、本書には他にも私にとっては初めての作品が納められていた。メインディッシュとして登場する1970年代のソ連旅行についての鼎談もその一つだし、初出が全国焼肉協会「月刊やきにく」、上野のれん会「月刊うえの」というのもある。引き出しの多いエッセイストだけあって、執筆依頼も多岐にわたっていたのだろう。
*
米原万里をよく理解している佐藤優氏だからこそできたフルコースを堪能しながら、この二人の接近に間接的に遭遇したおよそ20年前のことを思い出した。
もう時効だし、佐藤氏が『文藝春秋』(2008年10・11月号)でつまびらかにしているので、書いてもかまわないだろう。1993年に日本で出版されたレフ・スハーノフ『ボスとしてのエリツィン』(川上洸訳、同文書院インターナショナル)の第10章は、スハーノフではなく、万里さんの執筆だ。
Tweet |
||
| 1 ,2 >次へ |
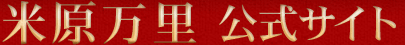
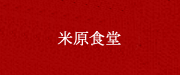
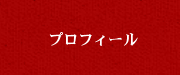
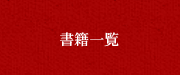
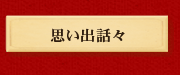



 PageUp
PageUp