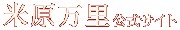このページでは、米原万里ゆかりの方が思い出を披露してくださいます。
2016.6.14 ◆黒岩幸子 米原万里さん没後10年の新刊書に寄せて(2) 本の中では日本語版の刊行にあたり、大統領補佐官だった著者スハーノフが口述筆記で付け加えたことになっている。その内容は、1992年にエリツィンが訪日をドタキャンした原因は、直前に訪ロした日本外相の強硬な態度や日本外務省のロシア情勢にかんする無知にあったという暴露だ。 ロシア側から出た秘密文書をもとに万里さんが一晩で書き上げたそうだが、9章までと筆致はまったく同じで、信じられないほど自然な仕上がりだ。「警備上の問題で訪日延期」という当時の公式発表の裏に日ロ外交の齟齬があることは、子どもでもわかっていたし、不審に思う一般読者はいなかっただろう。 このことを私が佐藤氏から知らされたのは1997年のことだ。万里さんがあっさり、「あれは私が書いたのよ」と告白したというのだ。当時まだ現役外交官で、「対ロ外交のためなら命捨てます」という勢いで働きまくっていた佐藤氏を知る者として、私は万里さんのことが心配になった。日本外務省の顔を潰すようなあの第10章の書き手を、佐藤氏が放っておくだろうか、何か陰湿なしっぺ返しをやるんじゃないかと。でもこれは杞憂だった。その後、佐藤氏は「米原さんは、ほんとは生まじめな人だ」と言ったきりで、何事も起こらなかった。 それから数年後、今度は心配すべき対象は万里さんではなく、鈴木宗男スキャンダルに連座して東京拘置所の住人になった佐藤氏になった。その頃の万里さんの佐藤優評は、「彼は実務には向かない、あまりにのめり込んで拘置所に行くようなことになっちゃうから。作家になればいいのよ、作家なら何を考えて何を書いてもバーチャルな世界だから大丈夫」。ついでに、私にも「創作」事件を披露、「それで、そのときモスクワにいた某ロシア大使があの本を床に叩き付け怒ったらしいのよ、アハハハ…」 いくらなんでも、それはまずいでしょう、下手したら笑って済まされない外交問題になったかも。それにロシア側の工作に加担したのかもしれないし…。と苦言を呈したかったが、なぜか私は万里さんの前では気が弱くなって逆らえない性癖があるので、言葉は全部飲み込んで薄ら笑いでごまかしてしまった。 でも今になってみると、あんな大胆不敵なことができる人が去っていったことが寂しい。今の日本を見回せば、まだ権力の介入が始まってもいないのに、もう同調圧力に屈して自己規制に走る言論ばかりだ。彼女が生きていたら、ここ10年の日本に向かって猛烈な異議申し立てを発信し続けただろう。 ネクラーソフは、詩人としてだけではなく、雑誌『同時代人』、『祖国雑記』の編集発行者としても権力と社会矛盾に抵抗し続け、決して時代に迎合することがなかった。その彼は、フルコースを締めくくる食後酒にも登場する。選ばれたのはアルメニア産コニャック、このエッセイのタイトルが本書の題名でもある。 そこには、「対話すること、異議を差し挟むことを求めている」ネクラーソフの「私」がいる。そして、一番自由な言葉を発することをできるのは、どんな集団を代表することもない「偉くない〈私〉、一個人に過ぎない〈私〉」だ(364-365頁)。本書は、米原万里が、盟友、佐藤優に働きかけて現代日本に発したメッセージのように思える。 *
もちろん、ロシア語通訳協会に向けられたメッセージもある。メインディッシュに合わせて選ばれた赤ワイン・キンズマラウリ(「コミュニケーションという名の神に仕えて」)には、協会設立の経緯や通訳者の適性などが語られている。若手協会会員のみなさんに、ぜひ読んでいただきたい。
協会の財政が窮地に陥った昨年はじめ、私は本気で協会解散、事務所閉鎖を考えていた。今の事務所は、家好きの万里さんが探し出したものだ。ああ、そこを畳んだりしなくてほんとうによかった。諦めて手放したりしたら、万里さんからどんな毒舌が浴びせられることか。存続に協力してくださったみなさんに深謝。そして、みなさんが、一番自由な「私」としてこれからも協会に関わってくださることを切に願っています。
2016年4月  2002年11月盛岡にて
Tweet |
| 前へ< 1 ,2 |
| プロフィール 黒岩幸子(くろいわゆきこ) |
| 佐賀市生まれ。慶應義塾大学卒、早稲田大学大学院修士課程修了。1983-1986年、日本航空モスクワ支店勤務。ロシア語通訳・翻訳業を経て1998年から岩手県立大学助手、現在は同大学教授。専門分野は日露関係、ロシア語教育。2015年からロシア語通訳協会会長。著書:『千島はだれのものか』(東洋書店、2013年)など。 |
|
『思い出話々』とは 米原万里のエッセイ「単数か複数か、それが問題だ」(「ガセネッタとシモネッタ」所収)に由来する。 ロシアからやってくる日本語使いがそろいもそろって「はなしばなし」という奇妙な日本語を口走る。(略)…この日本語もどきの版元が判明した。日本語学の第一人者として名高いモスクワ大学某教授。 「日本語の名詞にはヨーロッパ諸語によくある複数形はない。しかし一部の名詞にはインドネシア語などと同様、反復することによって複数であることを示すルールが適用される。たとえば、花々、山々、はなしばなし……」 |
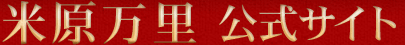
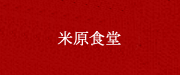
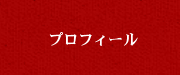
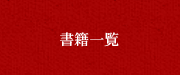
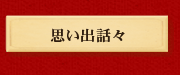


 PageUp
PageUp